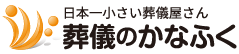般若心経とは。262字のお経に込められたこの世の真実
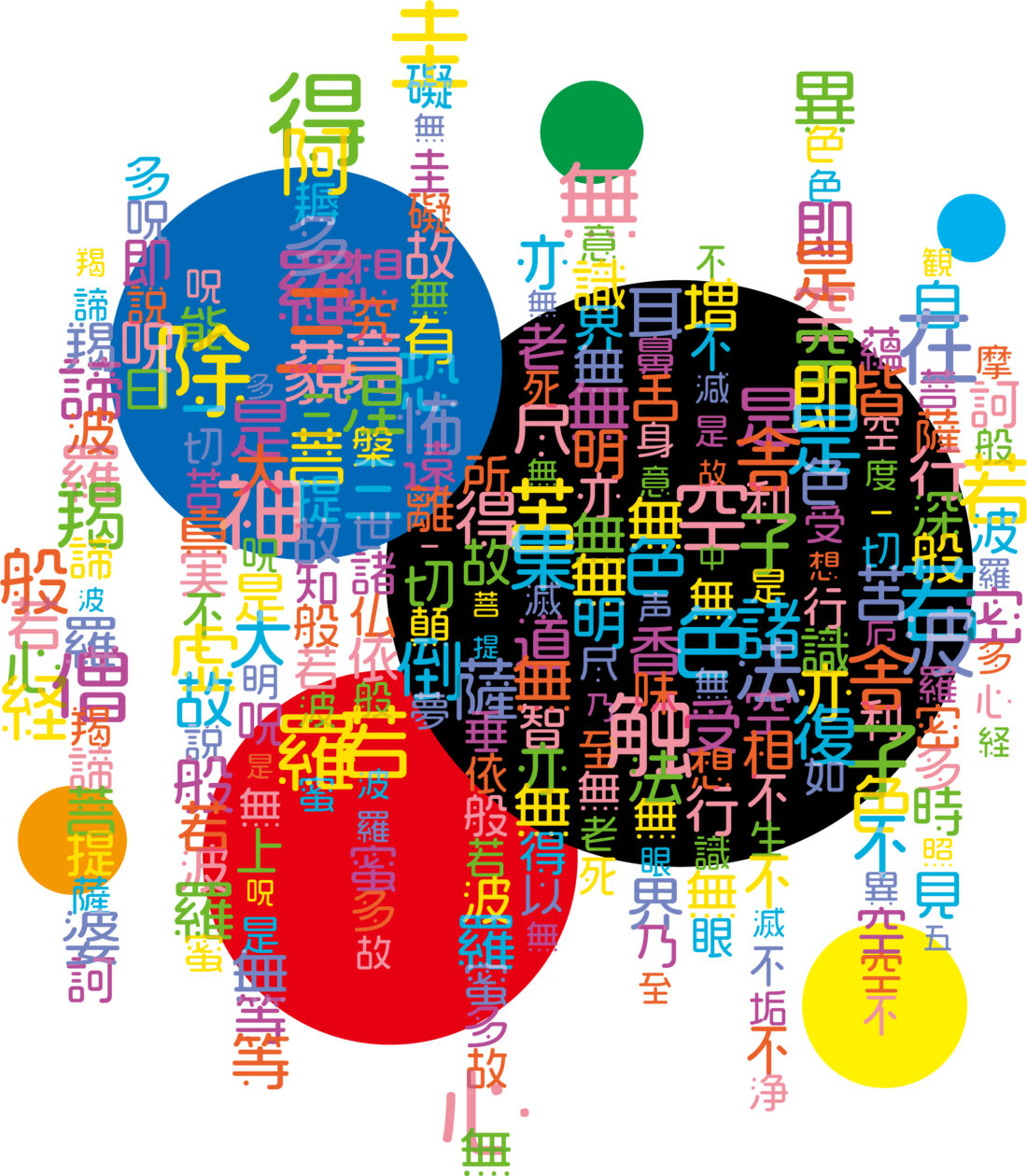
皆様こんにちは![]()
相模原市の葬儀社・神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。
仏教を知らない人でも、なんとなく聞いたことのある『般若心経』。いったいどういうお経なのでしょうか。
「色即是空 空即是色」
…ということばはとても有名ですが、「色は空で、空は色って、どういくこと!!」と思わずツッコミを入れたくなります。
そんな『般若心経』について調べてみましたので、どうぞ最後まで読み進めてみてください。
般若心経とは
『般若心経』は、日本でいちばん有名なお経のひとつです。
お葬式や法事でもよく耳にしますし、「ああ、これ聞いたことある」と感じる方も多いでしょう。お寺好きの方の中には、般若心経を諳んじることができる人も少なくありません。
般若心経の本文は、たった262文字です。にもかかわらず、仏教の核心である「空(くう)」という考え方が、ぎゅっと凝縮されています。
「空」とは、「すべてのものは、固定した実体を持っていない」という意味。
たとえば「自分」という存在も、「物体」や「感情」や「記憶」など、さまざまなものが一時的に集まっているだけ。それらが少しでも変われば、「自分」という存在そのものも変わってしまう。だから「これこそが絶対の自分!」というのは幻想なんだ、というのが「空」の考えです。
分かるかな…。
目の前に山があります。それは絶対に山で間違いありません。
でも、山にどんどん近づいていくと、木があり、岩があり、土があり、石がありと…山はただひとつの山なのではなく、いろいろなものがつながりあった集合体としてそこにあることが分かります。
山はあるけど、山そのものはない。
山そのものはないけど、でもいろんな集合体として山はある。
これを、般若心経の中では「色即是空 空即是色」としています。
この「空」を理解することで、自分という存在そのものへの執着を手放すことができ、それによって私たちは「解脱=自由」になれる。それが般若心経の教えです。
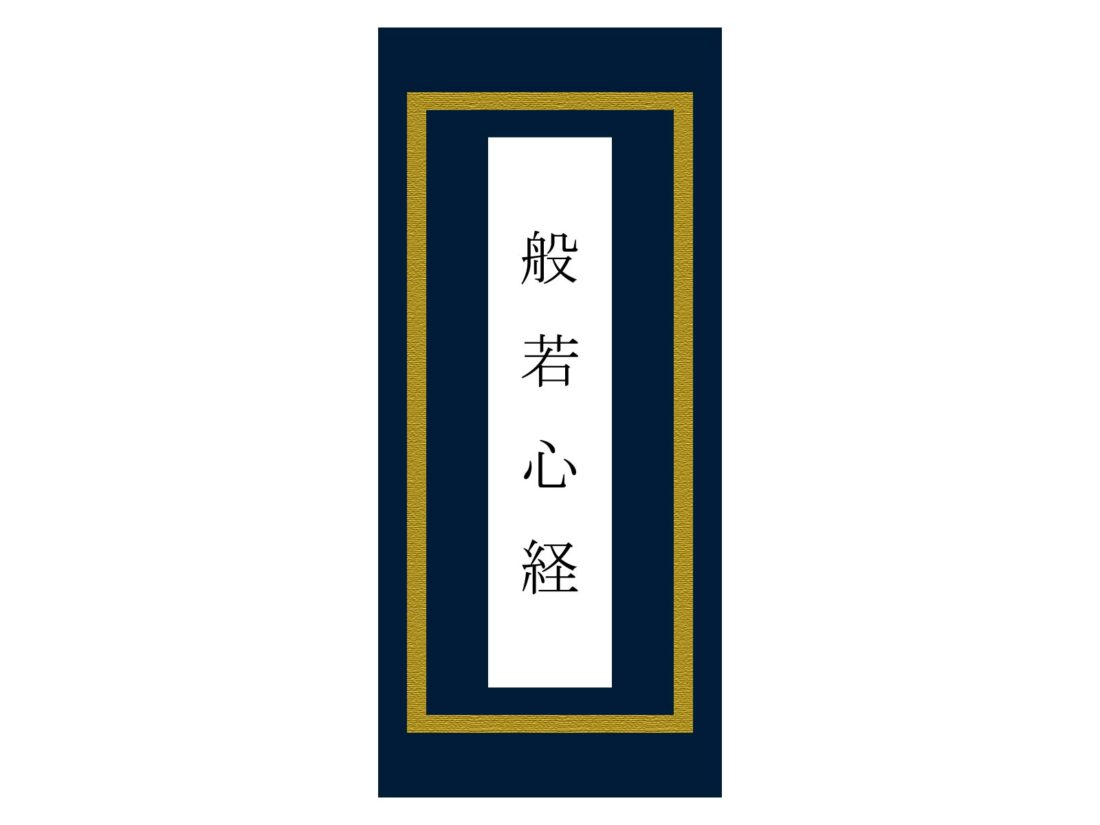
般若心経の全文解説とかなふく訳
般若心経の全文は以下の通り。『西遊記』でおなじみの、玄奘三蔵が訳したものになります。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経
観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄
舎利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是
舎利子是諸法空相不生不滅不垢不浄不増不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意、無色声香味触法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明尽乃至無老死亦無老死尽無苦集滅道無智亦無得
以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離一切顛倒夢想究竟涅槃三世諸仏依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真実不虚故説般若波羅蜜多呪
即説呪曰羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶
般若心経
これを、とてもとても僭越ですが、かなふく鈴木なり、現代語風に解釈して、訳したいと思います![]()
<かなふく風 般若心経現代語訳>
あるとき、観音さまが深く深く「本当の知恵」をたずねる修行をしておられました。
観音さまは、五蘊(わたしたち人間をつくっている5つのはたらき「心と体」「感情」「考え」「意志」「気づき」)をよく見つめて、こうおっしゃったんです。
「どれもこれも、ほんとうは空(からっぽ)なんだよ」と。
よく聞いてくださいね。
色(物質)というものは、空(からっぽ)なもの。
でも、空(からっぽ)というのは、何もないというわけではありません。
色と空は同じものなんです。色は空となり、空は色となる。
心のはたらき(感じる(受)、考える(想)、行動する(行)、気づく(識))も、まったく同じです。
この世界のすべては「空」を本質としています。
生まれることもなければ、消えてしまうこともない。
汚れることも、きれいになることもない。
欠けもしないし、満ちもしない。
だからこそ、空の立場から見ると──
物質も、感情も、思考も、意志も、気づきも、ない。
見る目も、聞く耳も、嗅ぐ鼻も、味わう舌も、触る体も、感じる心もない。
見る対象、聞こえる音、匂い、味、触れるもの、意志や想いも、ない。
目に映る世界も、心が認識する世界も、ない。
知識もなければ、煩悩もない。
であるなら、知識の消滅も、煩悩の消滅すら、ない。
苦しみから悟りにいたる道もない。
であるなら、真理を知ることも、悟りを獲得することもありません。
「ない」「ない」「ない」ばかりで寂しく思うかもしれませんが、だからこそです。
すべてが空であり、「私」という概念すらない、世界と自分を隔てるものがない世界というものは、とてもすがすがしいものです。
この智慧によってわだかまりがなくなることで
恐れることもなく、誤った見方からも自由になって、
こころの安らぎである「涅槃」に、静かにとどまっていられるのです。
過去・いま・未来のすべての仏さまたちも、
空という完成された智慧(=般若)をよりどころとして、
心を安らかにされています。
だから、はっきり覚えておきましょう。
この「般若波羅蜜多」という智慧は、
真実であり、偉大であり、
これほど確かなものはなく、
人生のあらゆる苦しみを乗り越える道しるべなのです。
それは、うそではなく、本物です。
だからこの言葉を、訳することなく、そのままの言葉で、心にとなえてみてください。
ギャーテー ギャーテー ハーラギャーテー ハーラソウギャーテー ボージーソワカー
──「行こう、行こう。彼岸へ渡ろう。すべてを超えて、ほんとうの目覚めへ。しあわせでありますように。」
これが、般若心経の教えです![]()

どうして般若心経がお葬式で読まれるの?
『般若心経』は、お葬式でよく読まれるお経です。でも、それはなぜなのでしょうか。
般若心経というのは、存在の真実を説いていると言えます。
つまり、いま、自分がここにいることは何を意味しているのか。
自分が見て、聞いて、嗅いで、味わって、触って、そして考える世界とはいったい何なのか。
その本質が説かれる般若心経が、なぜお葬式で読まれるのでしょうか。
それは、般若心経の説く空の教えが、生きている人、亡くなっている人を救う力を持っているからだと思います。
般若心経の教えに照らし合わせるならば「生も、死もない」「生はまた死であり、死はまた生である」とも言えますよね。
これって、一見冷たいニヒリズムに聞こえますが、よくよく考えると、悲しむに暮れるご家族や、亡くなってしまった故人さまにやさしく寄り添う教えだと思うんです。
また、「天国にいけるよ」「神様が待っているよ」というような、死後の世界の明るい物語を語るわけでもない。
死の苦しさ、死の寂しさを受け止め、克服するのは、あくまで自分自身の認識次第なのだと言っているわけです。そこがとても仏教らしいですよね。
日本のお葬式では、死者を仏弟子として、新たな世界に送り出します。
仏弟子がはじめに習得すべき教えこそが「般若般若波羅蜜多」の智慧なのです。
僧侶でも学者でもない、いち葬儀屋の私が『般若心経』について語らせていただきました。
けれども、この262文字の教えには、世界の本質が込められています。262文字なんて、ちょっと読み続ければすぐに覚えられます。経本も数百円で販売されています。
お寺で、お仏壇で、お墓で、どうぞ般若心経を唱えてみてください。そしてお葬式の時もお唱えすることで、あなたの般若心経に触れた故人さまの魂は、喜びに震えて下さることでしょう。