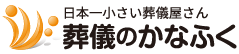お祭りの季節に「葬祭」について考える

カラオケの十八番は北島三郎の『祭』。
皆様こんにちは![]()
お祭り男でおなじみの、神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です![]()
日本人は本当にお祭り好き。秋にもなると、五穀豊穣への感謝を込めて、日本中のあちこちで秋祭りが開かれます。
ところで、ぼくたちの社名「神奈川福祉葬祭」にも、実は「祭」の文字が入っていることにお気づきでしょうか? そう、「葬祭」の“祭”です。
今日は、この「お祭り」と「葬祭」の関係について、少し考えてみたいと思います。
日本人はお祭り好き
日本では、春夏秋冬を問わず、全国各地でさまざまなお祭りが開かれています。
ここ相模原でも、夏の風物詩といえば「上溝夏祭り」。
このお祭りは江戸時代から続く由緒ある行事で、「須佐之男命(すさのおのみこと)」を御神輿に祀り、町内の疫病退散と安全祈願のために行われてきました。
宵宮と本宮の二日間にわたって、20基を超える神輿が町内を練り歩きます。上溝の商店街には数百もの露店が立ち並び、まち全体が熱気に包まれますよね。
御神輿には神様が宿り、年に一度、ぼくたちの町を歩いてくださいます。
「神様は遠い存在ではなく、身近な場所にいてくれているんだな」と実感できる瞬間です。
日本中のお祭りも基本は同じ形。神社に祀られる神様を御神輿に乗せ、町を巡っていただく。お祭りは神様と人との交流の場なのです。

祭りには礼拝の対象がある
改めて考えると、「祭」には必ず礼拝の対象があります。
その対象は大きく分けて3つです。
- 自然 … 山や森、川や海など身近な自然。
- 神話の神々 … 須佐之男命など、日本の神話に登場する神様。
- ご先祖様 … 遠い祖先が氏神として祀られた存在。
日本人はこの三つの要素をうまく融合させてきました。自然信仰から生まれた神、神話の物語の神、そして人間が亡くなったのち神へと昇華していく信仰。
「祭」とは、本来こうした存在に感謝し、交流するための儀式なのです。
そう考えると、相模原三大祭りのうち、本当の意味で「祭」と呼べるのは、やはり上溝夏祭りかもしれません。「橋本七夕まつり」や「相模原納涼花火大会」なども楽しい行事ですが、そこに礼拝の対象はなく、娯楽の要素が強いイベントだからです。
なぜ「葬」+「祭」なのか?
ここから本題、「葬祭」について考えてみましょう。
「冠婚葬祭」という言葉がありますよね。これは人生の大きな節目を示す言葉です。
冠 … 成人の儀式(元服・成人式など)
婚 … 婚姻の儀式(結納・結婚式)
葬 … 死の儀式(葬儀・埋葬)
祭 … 祖先を祀る儀式(法事・お盆など)
「葬祭」とは、一つの言葉のように使われますが、本来は「葬」と「祭」という別々の意味を持つ儀礼を表しています。
注目したいのは「祭」の意味。祭というのは、神様や仏様に限らず、亡き家族やご先祖を祀ることをも指します。しかも日本では、故人が時を経て神や仏に昇華していく、独特の宗教観を持っています。
葬儀は「葬」であり、時間が経てばそれは「祭」に変わっていく。だからこそ「葬祭」とは、人の死と、その後の祀りをひと続きにとらえた言葉なのです。
葬儀に神や仏が必要な理由
最近では「無宗教葬」が増えています。音楽を流し、花を飾り、自由にお別れをするスタイルです。時代に合った柔軟な選択肢として、それも尊重されるべきだとぼくは思います。
ただ、葬儀の現場に長く携わってきた立場から申し上げると、やはり葬儀には「神や仏」という拝む対象があった方が良いと感じています。
その理由は二つあります。
- 拝む対象があることで、葬儀が祭祀へとつながるから。
神仏を通して手を合わせることで、葬儀は単なる別れの場ではなく、供養の連続性を持った「葬祭」へと昇華していきます。
- 故人もやがて神仏となり、ぼくたちを守ってくれるという救いになるから。
神仏が「守ってくれる存在」であると同時に、亡き人もまた神仏になっていく。これが、二重の意味での救いになってくれると思うのです。
「人の一生は葬儀でおしまいじゃない」というのが、この冠婚葬祭ということばに含まれた深い意味だと思います。「葬」のあとに「祭」があるということは、葬儀のあとも、家族や子孫たちの中で故人は生き続けていることを意味するからです。
肉体は滅びても命のつながりは消えません。法事やお盆といった行事は、その命の流れを家族のなかで受け継ぐための大切な営みです。祈りを続けることで、亡き人の存在は絶えることなく息づき、日々の暮らしを支えてくれるのです。
この「生命の連続性」こそが、悲しみを受け止める大きな器となり、ぼくたちに安心と希望を与えてくれるのだと感じます。

おわりに
お祭りの季節になると、街はにぎやかで、心も弾みます。
けれど「祭」という字を見つめ直すと、その背景には「祈り」や「礼拝」という、人の営みの本質が隠れています。
葬儀とお祭り。一見正反対のように見えますが、どちらも「人と神仏を結ぶ場」という点で共通しているのです。
祭りを楽しみながら、ふと「葬祭」のことを思い出す。そんな視点で日常を見直してみるのも、また豊かな気づきになるのではないでしょうか。
神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)
代表取締役 鈴木 隆![]()
フリーダイヤル:0120-82-0333