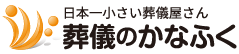お仏壇は必要なのか。葬儀屋さんが本気で考えました。

皆様こんにちは![]()
神奈川県相模原市の葬儀社・神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。
「最近は仏壇を置かない家も増えましたね」—―そんな話をお客様から聞くことが多くなりました![]()
たしかに、現代の住まい事情やライフスタイルを考えると、仏壇を置くスペースがなかったり、「宗教的に構えたくない」という声も理解できます。
でも、ぼくはこう思うんです。
「お仏壇って、信仰だけのものじゃなく、”想いを形にする場所”なんじゃないか」と。
今日は葬儀屋さんとして、そして一人の人間として、「お仏壇は本当に必要なのか」について、まじめに考えてみたいと思います。
■お仏壇に祀られる2つの「仏」
そもそも「お仏壇」とは読んで字のごとく、“仏”の祭壇です。
そして、ここで言う「仏」には二つの意味があります。
ひとつは、宗派ごとのご本尊。
「釈迦如来」「阿弥陀如来」「大日如来」など、それぞれの宗派で大切にしている仏さまが祀られています。
お坊さんをお呼びして法要を行うときには、その宗派の教えに基づいた儀式を行うため、ご本尊が必要になります。
もうひとつの「仏」は、亡くなられた故人さまご自身。
日本では、亡くなった人は、遺された家族たちの礼拝や供養を通じて「仏に成る」と考えられてきました。だから「成仏」と呼ぶわけです。
お仏壇とはつまり、仏教の仏と、成仏した仏の、2つの仏を祀り、いのちのつながりを確かめる場なのです。
■亡き人を思い出す。その思いを形に
人は誰でも、亡くなった人を思い出します。
「いま、どこで、何をしているんだろう」
「こんな時、あの人ならなんて言うかな」
そんな想いを胸に、心の中で故人さまに語りかける瞬間があります。でも、その想いは目に見えませんし、手でつかめるものでもありませんよね。
雲のように漂う心に、ちょっとした「実体」を与えてくれるのが、形あるもの。それが、お仏壇なのではないでしょうか。
たとえば「お誕生日おめでとう」ということばは目には見えません。でもそこに、形あるプレゼントを添えることで、より想いが伝わりますよね。
「何が好きかな。喜んでくれるかな」
「どこで手に入るかな」
「いつデパートに買いに行こうかな」
このような、相手に向けられる想いや、そこにかける時間と言うものが、目に見える形で分かるのが、プレゼントの魅力です![]()
そしてそのプレゼントを見るたびに、その人によって込められた思いが蘇ってきます。
お仏壇も、きっと同じなのではないかと思うんです。
手を合わせる場所があることで、目に見えない故人さまへの想いが祈りという行為になりますし、その祈りに、よりしっかりと想いを込めることができます。
最近人気の「散骨」も素敵な方法ですが、一方で、「散骨したあとに、どこに手を合わせたらいいか分からない」という声もよく聞きます。
やっぱり人は「想いを向けるための確固たる場所」を必要としているんです。
お仏壇とは、まさにその確固たる場所である、故人さまへの想いを目に見える形にしてくれる心の拠りどころなんですね![]()
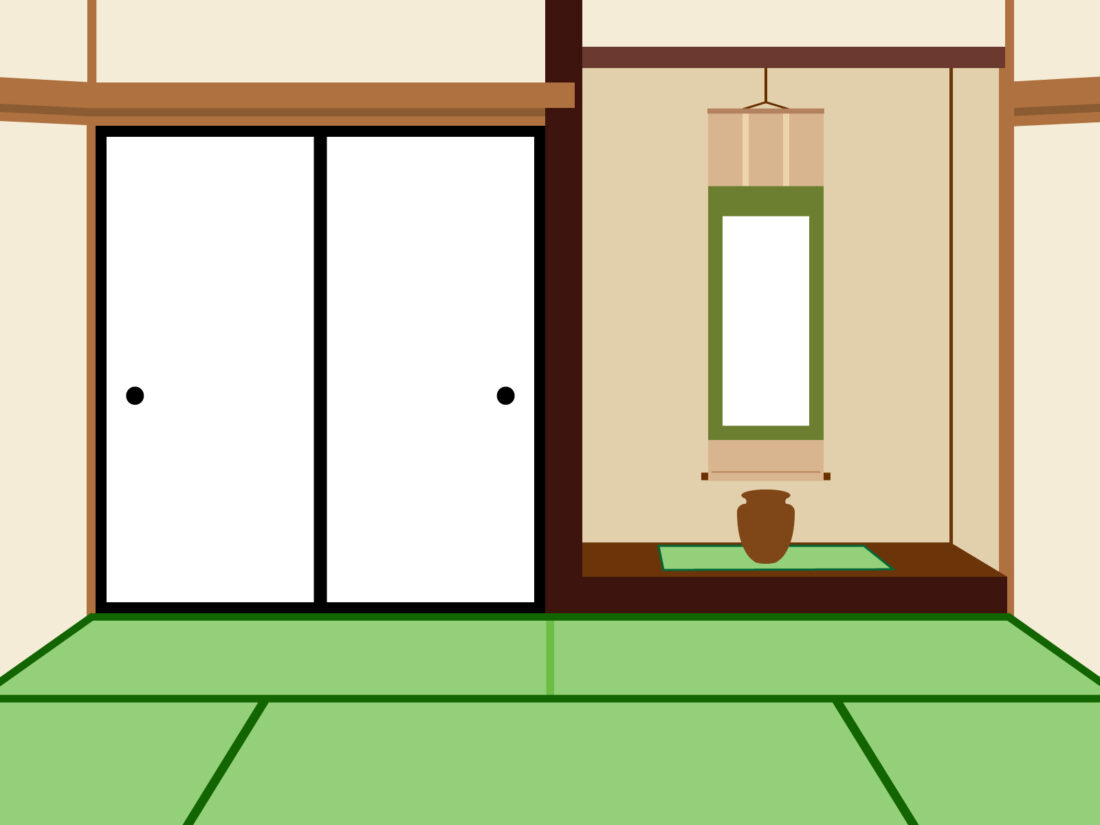
■「伝統かモダンか」よりもっと大事なこと
最近は、仏壇もさまざまです![]()
黒檀や紫檀の伝統的な仏壇から、リビングにも合うモダン仏壇、さらには小さなメモリアルスペースまで、本当に多様です。
じゃあ、どれを選べばいいのか。結論から言えば、ぼくは「どれでもいい」と思っています。形、デザイン、大きさなどは、さほど問題じゃないからです![]()
むしろ大事なのは、お坊さんを呼ぶか呼ばないか。ここじゃないでしょうか。
お坊さんをお呼びするなら、ご本尊を祀る仏壇を。そうでないなら、写真や思い出の品を飾るメモリアルスペースを。どちらも「祈りの場所」であることに変わりはありませんが、お坊さんがいる、いないで選ぶべきものも大きく変わってきます。
そして、さらに大事なことがあります。それは…
「自由やオリジナルは、時に迷いを生む」
…ということです。
「これでいいのかな」
「ちゃんと供養になっているのかな」
そう感じた時、自由な方法、オリジナルなスタイルに対して、迷いが生じます。迷いが生じると、故人さまへの想いがまっすぐ届かなくなります。
こういう時こそ、「伝統知」が役立ち、その象徴が、お寺であり、お坊さんなのです。
お坊さんのことば、所作、読経の声。それらは、何百年も続く祈りのかたちであり、不安を安心に変えてくれる道しるべでもあります。
自由な供養もいいけれど、自分の方法に迷った時、自分の心が故人さまにつながっていないかもと感じた時には、やはり長く続く伝統という智慧が。私たちを支えてくれるんです。
■学べる後ろ姿があるのはありがたい
伝統って、むずかしい言葉のように聞こえますけど、よくよく考えたらとても身近なものです。なぜなら、親子、師匠、先輩後輩の中で受け継がれていく姿そのものだからです。
そういう意味で、ぼくには学ぶべき親の後ろ姿というものがあって、いま思うとそれがとてもありがたいですね。
父はよく仏壇の掃除をしていましたし、母はご飯を炊くと、真ん中の一番おいしい部分を「一番飯」として仏さまにお供えしていた。そんな2人の後ろ姿をよく見ていたんです。
おそらく、子どもだったぼくは知らないうちに「祈りの作法」を学んでいたんでしょうね。それが無意識にぼくを葬儀屋さんに導いてくれたのかもしれません。
最近の研究で、「仏壇のある家で育った子は、自己肯定感が高い」という話もあるそうです。
毎日、誰かに手を合わせる時間があるというのは、それだけで「自分は見守られている」という安心感につながるのかもしれませんし、いざ自分が迷った時に、立ち返ることのできる場所や人があるというのは、大きな安心につながります。

■おわりに
今日はなんかものすごくまじめに書いてしまいましたが、まずはあなたが思う形で故人さまを偲ばれたらいいですよ![]()
お仏壇でも、メモリアルスペースでも、大丈夫です![]()
その上で、困った時、迷った時は、かなふく鈴木か、あるいは身近にいてくれるお坊さんに相談してみてください。
長く続いた伝統の智慧というものが、きっとあなたを支えてくれますよ![]()
葬儀のかなふく(株式会社 神奈川福祉葬祭)
代表取締役 鈴木 隆![]()