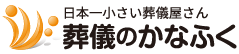【令和版】家族葬にふさわしい正しいお香典返しの方法

こんにちは。神奈川県相模原市の葬儀社、神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。
お葬式が終わって少し落ち着いた頃、「香典返しって、どうすればいいんだろう?」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。
「香典返しの費用っていくらくらい?」
「後返しと即日返しがあるって聞いた。どっちがいいの?」
「選ぶべき品物は?」
「カタログギフトって喜ばれるの?」
などの素朴な疑問を受けて、今日は葬儀の現場から、令和のいまに合った『家族葬にふさわしい正しい香典返しの方法』を、分かりやすくお話ししたいと思います
■香典返しとは
香典返しとは、葬儀の際にいただいたお香典へのお礼としてお贈りする品物のことです。
お香典には、故人を偲ぶ気持ちとともに「ご遺族の助けになれば」という意味が込められています。その気持ちに対して、感謝の心を形でお返しするのが「香典返し」なんです。
一般的には、「あとに残らないもの」が好まれるため、お茶や海苔、コーヒー、焼き菓子といった食品類が定番。
ほかにも、タオルやハンカチなど実用的な日用品、最近では贈る相手が自由に選べるカタログギフトも人気がありますね。
また、香典返しには大きく分けて二つの方法があります。
ひとつは、四十九日法要後にあらためてお贈りする「後返し」。もうひとつは、葬儀当日にお渡ししてしまう「即日返し」です。
後返しの場合は、忌明け(四十九日)を迎えたことを報告しつつ、改めて丁寧なお礼状を添えます。一方、即日返しでは、葬儀当日の「会葬御礼」と「香典返し」をまとめてお渡しする形になります。
この後返しと即日返しについてはのちほどくわしく解説するとして、まずは、香典返しの費用の目安について解説いたします。
■香典返しの費用の目安
香典返しは「半返し」が基本と言われてきました。
つまり、いただいた金額の半分ほどを目安にするという考え方です。
とはいえ、最近では3分の1程度でも十分に気持ちは伝わるとされています。
大切なのは金額よりも「感謝の気持ちがきちんと伝わること」です。
たとえば…
1万円の香典なら、半返しは5,000円、3分の1なら3,300円。
5千円の香典なら、半返しで2,500円、3分の1で1,500円ほど。
かなふくでは、お香典の平均を7千円と想定し(1万円と5千円の間)、2,500~3,500円程度の品をおすすめしています![]()

■【後返し】昔ながらの丁寧なお返し
後返しとは、葬儀を終えたあと、四十九日をめどにお贈りする香典返しのこと。昔からこの方法が一般的で、いまも「最も丁寧」とされています。
後返しのポイントは次の3つです。
・1件ずつお相手に合わせて品物を選ぶ
・四十九日法要の報告を兼ねた挨拶状を添える
・四十九日を終えて10日ほどで相手に届くようにする
お香典の金額は人それぞれ。5千円の方もいれば、1万円、あるいはそれ以上の方もいます。
ですから本来の香典返しは、その一人ひとりに合わせてお礼を考えるものでした。
また、かつてはご近所やお勤め先など、多くの方が葬儀に参列されていました。
「無事に四十九日を終えました」というご報告を兼ねてお礼をする――後返しには、そんな役割も、込められていたのです。
■【即日返し】ご家族の負担を減らす現代の方法
即日返しとは、葬儀当日に香典返しの品物をお渡しする方法です。ご遺族の負担を減らし、手続きや発送の手間を省けることから、近年は主流になりつつあります。
即日返しの特徴は次の3つです。
・葬儀当日に、お礼を完結できる
・葬儀後の遺族の負担が軽減できる
・香典金額の違いによる対応が必要
特に3番目の「香典金額の違いによる対応」…ここは注意しておきたいところです。
なぜなら、お香典って、人によって金額がさまざまですから。一律の品物では「お返しが足りない」と感じられることもあります。
そのため、実際の現場では次のような二つの方法がとられています。
<1:高額の方には、後日改めて追加の品物を贈る>
たとえば、香典金額の平均を7千円と想定し、3千円程度の品物を用意していたとします。
その中に、5万円のお香典を包まれた方がいた場合、同じものをお渡しするだけでは失礼にあたるため、葬儀後に追加の品物を改めてお贈りします。
<2:会場に金額別の品物を複数用意しておく>
地域や葬儀社の方針によっては、葬儀会場に、金額別に応じた品物を複数用意しておくという方法も見られます。
葬儀会場の受付で香典袋を開けて、中身を確認して、金額に応じた引換券を渡します。参列者は帰り際にその引換券と品物を交換するという流れです。
この方法は効率的で分かりやすい反面、参列者の帰りの荷物が増えてしまったり、引換所が混乱するなどの注意点もあります![]()

■後返しと即日返しはどっちがいいの?
かなふく鈴木は「後返し」を勧めています。
葬儀当日はいろいろとバタバタするので、喪主が準備すべきもの、参列者が持って帰るものは、極力少ない方が、ストレスフリーにつながり、いいかなと思います。
また令和のお葬式だと家族葬が多いですから、葬儀後の品物の選定もそこまで時間がかかりません。
香典返し本来の意味を形にできるので、対応としても丁寧なのではないでしょうか。
■カタログギフトの注意点
最後に、近年のトレンドのカタログギフトについて考えてみましょう。
もらった人が自由に選べる、贈る側も品物を一つひとつ決めなくてよいというメリットばかりのように思えますが、以外に注意点もあります。
まず、受け取った方にひと手間かけてしまうということ。品物を選ぶ、商品の手配をするという手間を、相手に委ねちゃうということです。
面倒臭がり屋の方や、お仕事が忙しくてなかなか自宅に帰れない方などに、充分に品物が届かないことがあります。
また、品物もクオリティもさまざまです。たとえば1万円の香典をされた方に3千円程度のカタログを贈ったとしましょう。
3千円程度の時計やバッグなどとなるとそのクオリティたるや…という感じです。
ということを考えると、無難なものを喪主側で決めて贈っても、それはそれでいいのではないでしょうか。
とはいえカタログギフトは便利で、令和のトレンドとなるでしょうから、だからこそ、こうした注意しておくべき側面も把握してもらいたいものです。

■おわりに
香典返しには、「感謝の気持ちを形で伝える」という大切な役割があります。
即日返し・後返し、どちらの方法にもメリットがありますが、大切なのは無理のない方法を選ぶことです。
葬儀後の忙しい時期だからこそ、負担を減らしながらも、しっかりと「ありがとう」を伝える工夫が求められます。
相場や品物選びに迷ったときは、葬儀をお手伝いした葬儀社に相談してみてください。
神奈川県相模原市にお住まいの方は、葬儀のかなふく・神奈川福祉葬祭の鈴木までお気軽にご相談下さいね。
ご家族の状況に合わせて最適なお返しの方法をご提案しています。
形式にとらわれず、心を込めた香典返しを一緒に考えていきましょう!
葬儀のかなふく(株式会社神奈川福祉葬祭)
代表取締役 鈴木隆![]()