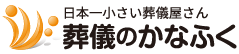葬儀の忌み言葉と、本当のマナーを考える

こんにちは。神奈川県相模原市の葬儀社、神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。
お通夜や告別式に参列すると、喪主や遺族になにかお悔やみの言葉をかけなくてはと思いつつ、どんな言葉をかければいいのだろうと、言葉が詰まる時ってありませんか?
さらには、声をかけようにも…
「こんなことを言っていいのかな」
「どう表現すればいいのだろう」
「言って失礼な言葉ってあるのだろうか」
…などと考えてしまうと、うまく話せなくなるものです。たとえ悪気がなくても、思わず口にしたひと言がご遺族を傷つけてしまうことだってありますもんね。
葬儀の現場には、避けるべき言葉「忌み言葉」というものがあります。今日は、この「忌み言葉」を中心に、言葉のマナーについて考えてみたいと思います。
■忌み言葉とは
「忌み言葉」とは、死や不幸を連想させる言葉、または「不幸が続く」ことをイメージさせる言葉のことです。
同じように、結婚式などの祝い事でも「別れ」や「再び」などを避ける習慣がありますが、葬儀の場では特に慎重さが求められます。
日本には、古くから「言葉には魂が宿る」という考え方があります。みなさんも聴いたことあるかもしれませんね。「言霊(ことだま)」です。
そのため、葬儀の場では「自らが発した言葉で悲しみが連鎖しないように」という願いをこめて、言葉を選ぶのです。
忌み言葉は、単なるマナーではなく、相手を思いやる「祈りのかたち」でもあるんですね。
■葬儀で避けたい代表的な忌み言葉
では、実際にどんな言葉を避けるべきなのでしょうか。代表的な例をいくつか紹介します。
<1.不幸や死を直接連想させる言葉>
「死ぬ」「生きていたころ」「ご愁傷さまですが」「災難」「消える」「落ちる」など、死や不幸を強く思わせる言葉は控えます。
代わりに「お亡くなりになられた」「ご逝去」などの表現を使うと穏やかです。
<2.繰り返しを意味する言葉>
「また」「重ね重ね」「再び」「くれぐれも」「ますます」などは、「不幸が繰り返す」と連想されるため避けます。
つい口癖のように言ってしまいがちですが、お葬式の現場では注意が必要です。
<3.縁起の悪い慣用句や比喩>
「浮かばれない」「最後まで」「終わりにする」「絶える」「切れる」など、命の終わりを思わせる言葉も避けましょう。
<4.手紙やメールで使わない方がよい表現>
「お元気ですか?」や「再会を楽しみにしています」などは、悲しみの状況にはふさわしくありません。
弔電やお悔やみ状では、「このたびはご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」といった定型の文面で十分です。

■香典や挨拶で注意したい言葉遣い
香典袋の表書きにも言葉のマナーがあります。
仏式では「御香典」または「御霊前」、四十九日を過ぎた後は「御仏前」とします。
神式では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」など、宗教によって表現が異なります。
また、お悔やみの挨拶でも「がんばってください」は避けるべきとされています。悲しみの中にいる方に向けて「がんばる」は酷な言葉です。
代わりに「どうぞご自愛ください」「無理なさらないでくださいね」と、寄り添う言葉が適しているとされています。
■なぜ忌み言葉を避けるのか
「どうして、そんなに細かく気をつけなきゃいけないの?」と思われる方もいるかもしれません。
でも、言葉って、空気を変える力があるんです。
人が沈黙しているときに何気なく言ったひと言が、その場の空気をやわらげたり、逆に冷やしたりする。
葬儀は、心のバランスが崩れやすい時間です。だからこそ、「この人は丁寧に言葉を選んでくれたな」と感じてもらえることが、何よりの慰めになるんです。
忌み言葉を避けるのは、ただの形式ではなく、言葉を選ぶこと自体が、相手への思いやりそのものを意味しているんです。
■マナーは、正しさより思いやりが大事
ぼくは、葬儀のマナーでいちばん大事なのは「正しさ」よりも「思いやり」だと思っています。
たとえば、言葉に詰まって何も言えなかったとしても、深く頭を下げるだけで十分伝わることがあります。逆に、どんなにきれいな言葉を並べても、そこに心がなければ、どこか冷たく感じられるものです。
マナーとは、「相手を思う心を形にすること」。その心さえあれば、完璧な言葉を覚えていなくても大丈夫ではないかとすら思います。
これまで忌み言葉について語ってきた内容をひっくり返すみたいで申し訳ないのですが、何より大事なのは「正しいマナー」よりも「相手へのおもいやり」です。
つい、「また」や「くれぐれ」などの忌み言葉を用いてしまったとしても、悪気がないことが分かれば、相手は特に気にしないでしょう。
お互いの関係性があるからこそ、「がんばって」というひと言が相手の支えになることだってあるでしょう。
マナーは、厳粛な儀礼の中で判断に困った時のためのひとつの指標みたいなもので、それが絶対ではありませんし、ただ正しく守っていればいいというものでもありません。
むしろ、マナー頼みにならず、自分の身体と頭と心で、
「相手はいまどういう想いなのかな」
「どういう言葉をかけると心がやわらぐかな」
…と察する努力こそが大事で、それが相手に伝わった時に、想いが通じ合うのではないのかなと、思うんです。

■おわりに
忌み言葉は、気づかぬうちに口にしてしまうことも多いですが、そういうものがあるんだと知っておくだけで、いざという時に相手を傷つけてしまう言葉を防ぐことができます。
言葉には力があります。相手を慰めも、傷つけもできるものです。
だからこそ、正しい言葉より、相手の心情を理解した上で寄り添えるひと言を。それが、葬儀のプロとして、ぼくがいちばん大切に考える言葉のマナーです。
本日も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました![]()
葬儀のかなふく(株式会社神奈川福祉葬祭)
代表取締役 鈴木 隆![]()