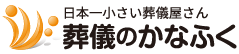七五三から「祈り」や「神頼み」について考えてみる
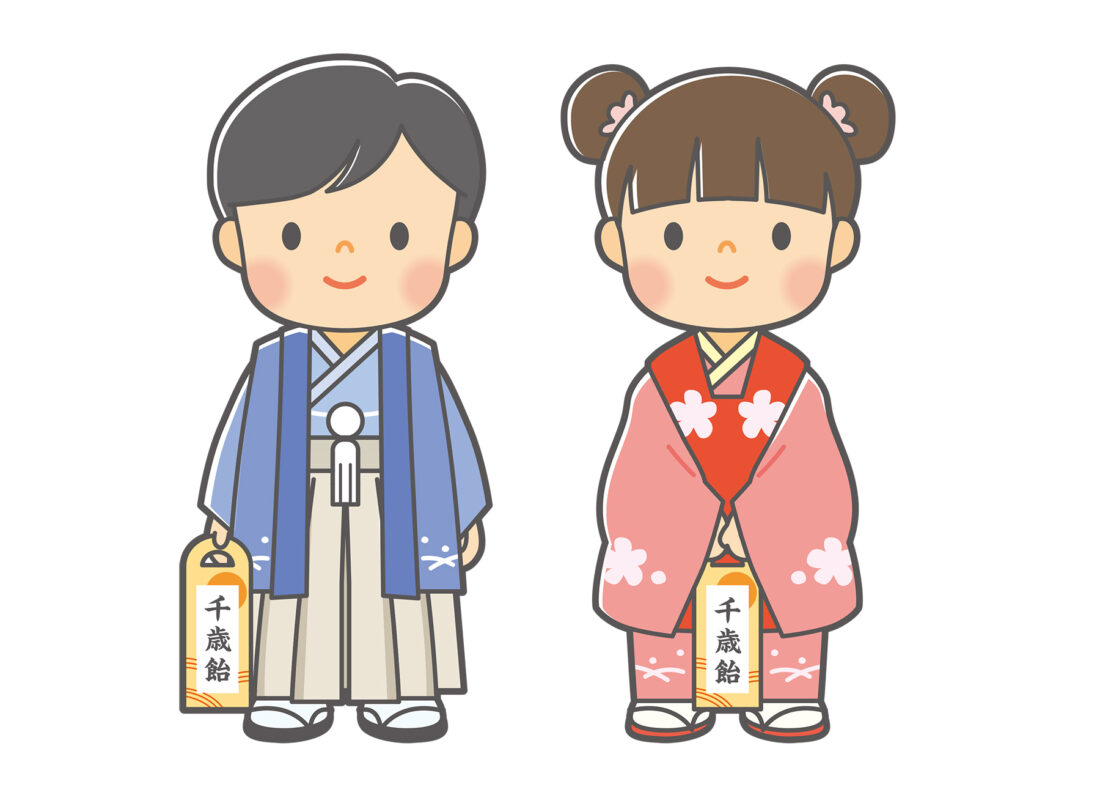
こんにちは。神奈川県相模原市の葬儀社、神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。
11月15日は七五三。神社の前を通ると、かわいらしい晴れ着姿の子どもたちを見かける季節ですね。
七五三は、3歳・5歳・7歳の節目に、子どもの健やかな成長を神さまに感謝し、これからの無事を祈る日本の伝統行事です。
昔は医療も未発達で、幼い命が危うかった時代が長く続いていました。
だからこそ、ここまで無事に育ってくれたという喜びと、これからも元気に生き抜いてほしいという願いを込めて、家族みんなで神社に詣でたのです。
言い換えれば、七五三とは生きることそのものを祈る日。七五三を迎えた子どもたちだけでなく、今を生きるぼくたちにとっても、とても大切な意味を持っているのです。
今日は、そんな七五三を通じて「祈り」について考えてみたいと思います。
■神仏に祈るということ
神社やお寺に出向いて祈る行事は、七五三に限りません。
初詣、節分、お彼岸、お盆、結婚式、厄除け祈願などなど。
ぼくたち人間は昔から、人生の節目やその年の節目迎えると、何かにつけて神仏に祈りを捧げてきました。
祈りって、「ああなってほしい」「こうあってほしい」と、自分が望む結果を願うことですが、同時に自分の力ではどうにもコントロールできないことを、より高次な存在である神や仏に委ねることでもあります。
「どうか、この子がいつまでもすこやかに育ってくれますように」
「どうか、この子が幸せでいられるよう守ってください」
このように、ぼくたちは神さまや仏さまにお祈りしますよね。
これってよく考えると「この世界には自分の力ではどうにもできない領域がある」ということを認める行為でもあります。
人間は、どこまでいっても不完全で、思いどおりにならないものです。
病気、事故、災害、大切な人との別れなど、そうしたものに直面したとき、人ははじめて、この世界がままならないことばかりで、自分がちっぽけな存在であることを知ります。
子どもの成長や幸せだって、どんなに親が願ったって、必ずしもその通りになるとは限らない。
その「ままならなさ」「ちっぽけさ」を認めることこそが、祈りのはじまりじゃないでしょうか。
「神仏」という高次な存在に向かって祈るという行為は、けっして迷信なんかじゃなく、むしろ人間の深い自己認識――いわば「メタ思考」のひとつなだと、かなふく鈴木は考えます。

■困ったときの神頼み、でいい
「困ったときの神頼み」と言うと、どこか軽い響きに聞こえますよね。
でも、ぼくはそれでいいと思っています。
だって、本当に困ったとき、人は自然と、何かにすがりたくなるじゃないですか。
心が折れそうなとき、まわりに頼れる人がいないとき、思わず空を見上げ、深く息を吐いて、目を閉じて、祈る。そんな経験、ありませんか?
それってもう、心のどこかに「自分を超えた何か」の存在(=神様)を頼っていることですよね。これだけで、充分神頼みなんです。
それは、宗教とか信仰とかいう以前に、人としての自然な反応ですよね。祈ることによって、自分の中の不安とか、不満とかを、いったん外に手放すことができる。
こう考えてみると、祈りや神頼みって、自分の願望を何かに託すだけでなくて、自分の心を整えるための行為でもあるとも言えるかもしれませんね。
■七五三に込められた祈り
こうやって、祈りや神頼みについて考えてみると、七五三の本質も、まさにそこにあることが分かります。
子を持つ親の本音って、
「愛するわが子がかわいすぎるからこそ、神仏の力を借りてでも、この子の無事を保証してもらいたい」
…というものじゃないでしょうか。
普段は信仰心を持たない人だって、かわいいわが子のためならいくらでも神頼みをします。
人間ってそんなもんだし、それでいいし、その素直な気持ちを、神社に詣でることで、家族みんなで共有できます。それこそが、七五三をはじめとする、神事や仏事の本質です。
神様に手を合わせて、頭を下げて、感謝を伝えて、お願いことをする。
「ここまで無事に育つことができました。本当にありがとうございます」
「これからも、どうかこの子が無事で健やかに大きくなってくれますように」
このように祈るその姿にこそ、人間の弱さ、やさしさの原点があるように感じます。

■祈りは、葬儀にも通じる
かなふく鈴木は葬儀屋さんですが、この祈りや神頼みの本質は、実は葬儀の中でも同じように生きています。
亡き人の安らぎを願い、手を合わせ、心を込めて、生前の感謝を伝え、あの世での安寧を願う。それは、七五三で神様にわが子の成長を祈る姿と、どこか重なります。
人の生き死にもままならないものですし、そうした事態に直面した時に、人間のちっぽけさを痛感させられます。
「人の力ではどうにもならないこと」を、僧侶や神仏の力を借りながら、なんとか受け入れようとする。葬儀での祈りもまた、亡き人のためであり、生きる私たちの心を整えるための儀式でもあるんです。
■おわりに
七五三も、葬儀も、そして日々の合掌も、その根っこにあるのは「祈り」です。
祈りとは、「人はとってもちっぽけで、この世は思うようにいかない」ということを知ることです。その気づきが、神仏の存在を認め、やさしさを生み、感謝を深めることにつながります。
今年の七五三を迎える親御さんたちには、子どもたちの笑顔を見守りながら、いつも以上に、心を込めて、神様に手を合わせてみてください。
その小さな祈りは、きっと大切なお子さんに届き、あなた自身の心をもあたためてくれるはずです。
今日もここまでお読みいただき、ありがとうございました。
神奈川福祉葬祭は、七五三の祈願はできませんが、葬儀に関する疑問や不安のご相談を承っています。いつでもお気軽にご相談くださいね。
葬儀のかなふく(株式会社 神奈川福祉葬祭)
代表取締役 鈴木 隆
フリーダイヤル:0120‑82‑0333